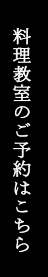先月、調理家電に関するインタビューのご依頼をお受けして、
企業の方やライターさんに、調理家電と料理について延々お話しし続ける、
というお仕事をしました。
(これが、時間が足りないくらい盛り上がりました。
何せ調理家電とは山のように仕事で付き合ってきたから!)
その際に、「単一機能しかない調理家電」の話になりました。
ただ「パンを焼く」だけのトースターとか、「燻製にする」だけの機械とか。
単一機能をとことん極めた高級家電も増えましたね。
そんな中、普段使っているもので、単一機能のものって他に何かあるかなあ、と考えていて
「精米機」を思い出しました。
これって究極の単一機能。
さすがの私も、精米することにしか使いません。
うちで使っているものは、確か1万円もしないくらいのちっちゃなものですが、
搗き具合も選べて、超便利。
私は普段は酵素玄米(玄米と小豆を炊いて発酵させたもの)を食べているのですが、
ピカピカの白米にしたいときは、ビューンと回せば搗き立てなのですごく美味しいし、
分づきにしたり、胚芽米にしたりと、使い勝手が良く、
何しろ精米ばっかりは手ではできない!ので重宝しています。
手の代わりにやってくれる機械、調理家電は今やどんどん進化をとげて
いろんなものが出てきていますね。
性能もどんどん上がっているので、機械に振り回されるのではなく(場所を取ることも含めて)、
うまく使いこなして、生活の質を上げたいものですね。
そのためには、温度と時間の知識(経験値)が欠かせないように思います。
精米機に話を戻すと、精米した後の新鮮なヌカ、これをちょこちょこ足していくと、
ぬか漬けがすごく美味しい。
でも毎日毎日かき混ぜて、漬物を食べるのは、ちょっと大変じゃありませんか?
温かくなってきたので、また今年もぬか漬けシーズンになりましたが、
最近私はぬか床を「冷蔵庫&常温行ったり来たり」で管理しています。
もともと出張中や、忙しいとき、ぬか床を冷蔵庫に移していたのですが、
手をかけられないから床を休ませるという発想をやめて、
むしろ冷蔵庫でゆっくり発酵させてみようと思ったら、
これがなかなかいい。
暑い時期に常温短時間でキリッと浅漬けにしたきゅうりなんか大好きなのですが、
2、3日くらいかき混ぜもせずに冷蔵庫で漬けた野菜も、
ゆっくり酸味を帯びてこれまた美味しいんです。
(乳酸菌が活性化する温度ではないけど、味をみると確かに乳酸発酵していると思う。
冷やす前に元気なぬか床にしておくことが大切かも。新鮮なぬかはそれを促してくれます。)
冷蔵庫では腐敗に傾きにくくなるから、床の塩分を強くしすぎなくても良いし、
何よりぬか床に振り回されないで済みます。
気が向いたら、常温に出して何日か床を活性化しつつ浅漬けを楽しんで、
また冷蔵庫に入れて、という感じで気楽に付き合っています。
忙しいけど自家製ぬか漬けを楽しみたい、毎日は食べないし塩分が気になるけど、発酵食品はとりたい、
という方に「冷蔵庫と常温の行ったり来たり」、オススメです。
日々の料理ライフの中で、「温度と時間」を味方につけたいですね。